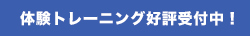現在地:HOME ≫ NEWS&TOPICS
【ブログ更新】Ⅱ型糖尿病のある方におすすめの運動方法と注意点
糖尿病のある方におすすめの運動方法と注意点

糖尿病と運動
2016年の国民健康・栄養調査では、20歳以上で糖尿病が強く疑われる人が1,000万人、
可能性を否定できない人が1,000万人、両方合わせて2,000万人と推計されています。
糖尿病の方は、そうでない方と比べて心臓血管系疾患のリスクが3倍高いと言われています。
糖尿病治療においては、適切な食事管理と運動療法が基本となります。
日本で増えている2型糖尿病は、インスリンの分泌不足という遺伝的な要因に加えて、
肥満、運動不足、加齢によるインスリン分泌不足といった環境的な要因が生じて発症します。
また日本人は欧米人に比べて糖負荷に対するインスリン分泌能力が低いという遺伝的要因もあるそうです。
肥満や運動不足は、分泌されるインスリンの抵抗性を増大させて、
高血糖状態をきたし、2型糖尿病を増加させます。
適切な食事管理と運動療法は、インスリンの抵抗性を改善させて血糖コントロールの改善が期待できます。
運動によるインスリン抵抗性の改善
運動によるインスリン抵抗性改善の仕組みを、詳しく説明します。
人の筋肉の細胞膜上(細胞の表面)には、「インスリン受容体」と言うインスリンの受け皿のようなものがあります。
そこにインスリンがくっつく(結合する)と糖の分子を運ぶ「GLUT(グルコーストランスポーター)4」と言うものが筋肉の細胞膜上に表れて、血液中の糖を筋肉の中へ取り込みます。
またそれとは別に運動により筋肉が収縮することで、「AMPキナーゼ」と言うものが活性化されて、
それによって「GLUT4」が筋肉の細胞膜上に表れるという仕組みもあります。
そのように、運動によって血液中の糖が筋肉の中に取り込まれて利用されることで、
血糖値が下がります(これを急性効果と言います)。
また、運動を長期にわたって続けることで、以下のような現象も起きてきます。
- 筋肉内の中性脂肪の減少
- 筋肉内の「GLUT4」の増加(発現量増加)とミトコンドリア数の増加によって、筋肉のインスリン抵抗性改善
- 内臓脂肪の減少によって、肝臓の中性脂肪の蓄積の抑制
- 内臓脂肪の減少と脂肪細胞が小さくなることによって、脂肪細胞から分泌されるアディポネクチン(動脈硬化などに対して予防的にはたらくタンパク質の一種)の分泌改善
そのような現象が起こることで、インスリンの抵抗性の改善が期待できます。
ただ、ここでとても大切なことですが、医師から投薬の治療を受けている方は、運動によって
低血糖や低血圧などを起こすリスクもあります。
ですので、運動開始にあたっては、必ず主治医に確認しましょう。

運動が禁止または制限される目安
運動を禁止、または制限した方が良い主な場合は以下の通りです。
- 空腹時血糖250mg/dl以上、またはケトン体中等度以上陽性
- 網膜症による眼底出血がある(眼科医と相談)
- 腎不全がある
- 虚血性心疾患、心肺機能に障害がある
- 骨・関節疾患がある
- 急性感染症
- 糖尿病塊疸
- 高度の糖尿病自律神経障害
2型糖尿病のある方におすすめの運動方法
それでは次に、どのような運動が効果的か?
についてお話ししていきたいと思います。
(また少し専門的な話しになりますが)
日本糖尿病学会の「糖尿病診療ガイドライン2019」には、運動療法について以下のように示されています。
- 週に150分以上、週に3日以上の有酸素性運動
- 1回の運動時間は少なくとも10分以上(できれば10〜30分程度かそれ以上)
- 運動強度は中強度以下(最大酸素摂取量の50%程度、または最大心拍数の50〜60%程度(50歳未満では100〜120拍/分、50歳以上では100拍/分未満が目安)、自覚的運動強度では「楽」〜「ややきつい」程度、Mets法では4〜6メッツ)
- 若年者や体力的に適合する人は、短時間(週に75分以上)の高強度有酸素運動も可能
- 運動をしない日が2日間以上続かないように行う
- 有酸素性運動に取り組むこととは別に、座位時間をできるだけ短くする
- 週に2〜3日(連続しない日)、8〜10種目の上半身と下半身のレジスタンス運動
- レジスタンス運動の負荷は、10〜15回(最終的には8〜12回)できる重さで1〜3セット
ただし、「個人の体力レベルや年齢、合併症、生活スタイルに合わせて始める」
と書かれてあります。
ですが、週に150分とか、週に3日以上とか、
さらに週に2回筋トレもするとか、すごくハードル高いですよね。
現実的に、上記の運動を実践できる人は少ないと思います。
ですから、糖尿病の方が運動を始める時には疾患のある方の運動指導について専門知識を持っている健康運動指導士にぜひ一度相談されることをおすすめします。
そして、今のご自身の体力や生活習慣の中で、どのような運動ができそうで、
どのくらい行えば良いのか、トレーニングプランを立ててもらいましょう。
糖尿病で服薬のある方が運動する際の注意点

服薬している薬の種類によっては、低血糖を起こしやすい場合がありますので、
運動を実施する時間帯など、主治医にも事前にしっかりと確認しましょう。
高齢で糖尿病のある方は、そうでない方と比べて筋肉量が低下しやすいことも示唆されていますので、
有酸素性運動とレジスタンス運動を組み合わせることも大切ですね。
服薬の種類によっても注意点が異なります。
薬の種類と注意点
糖尿病の薬の種類と服薬されている方が運動する際の注意点をお話しさせていただきます。
ご自身が服用している薬に照らし合わせて読んでみてください。
医師より糖尿病の方に処方される「経口血糖降下薬」には以下の2系統があります。
① インスリン分泌促進系
② インスリン分泌非促進系
前者①は膵臓に作用する薬でさらに
①−1 血糖依存性
①−2 血糖非依存性
の2種類に分かれます。
後者②は膵臓以外の臓器に作用する薬でさらに
②−1 小腸で糖の分解・吸収を抑えて、急激な血糖の上昇を抑制する薬
②−2 腎臓で血液から尿への糖の排泄を促進する薬
②−3 筋肉や肝臓などでインスリンの作用を高める薬
②−4 肝臓からの糖の放出を抑え、またインスリンの働きを良くする薬
に分かれます。
またその他に
③ 配合薬もあります。
主な経口薬は以下の通りです。
①−1
「DPP−4阻害薬」
インクレチンというホルモンの働きを強めて、インスリンの分泌を促す。
(ジャヌビア®︎錠、グラクティブ®︎錠、ネシーナ®︎錠、ザファテック®︎錠、メリゼブ®︎錠など)
「経口GLP−1受容体作動薬」
インクレチンの受容体に作用してインスリンの分泌を促す。
(リベルサス®︎錠)
①−2
「スルホニル尿素薬(SU薬)」
膵臓からのインスリンの分泌を促す。
(オイグルコン®︎錠、ダオニール®︎錠、アマリール®︎錠、アマリール®︎OD錠など)
「速効型インスリン分泌促進薬(グルニド薬)」
服用後短時間で膵臓からのインスリンの分泌を促す。
(グルファスト®︎錠、グルファスト®︎OD錠、シュアポスト®︎錠など)
②−1
「α−グルコシターザ阻害薬(α−GI)」
(グルコバイ®︎錠、ベイスン®︎錠など)
②−2
「SGLT2阻害薬」
(スーグラ®︎錠、アプルウェイ®︎錠など)
②−3
「チアゾリジン薬」
(アクトス®︎錠など)
②−4
「ビグアナイド薬」
(グリコラン®︎錠、メトグルコ®︎錠など)
③
スージャヌ®︎配合薬、エクメット®︎配合薬、グルベス®︎配合薬など
とてもたくさんの経口薬がありますね。
糖尿病の方が運動する上で特に気をつけたいことは、運動中の低血糖です。
①−2スルホニル尿素薬(SU薬)と速効型インスリン分泌促進薬(グルニド薬)は、
副作用として低血糖を起こしやすく、特に注意が必要です。
①−1DPP−4阻害薬もSU薬との併用において低血糖を起こしやすく、注意が必要です。
また、②−2SGLT2阻害薬は副作用として脱水症状を起こすことがあるため、
適度な水分補給を心がけることが大切です。
②−4ビグアナイト薬は、吐き気、嘔吐、下痢などの消化器症状の副作用があり、
高齢者で特に注意が必要です。
次は、薬の種類と体重についての関係、そして、実際に運動する際に注意する症状と
対処方法をお話しさせていただきます。
薬の種類と体重との関係

薬と体重の関係と、実際に運動する際に気をつける症状や、対処方法をお話しさせていただきます。
まずは薬の体重への影響について。
①−2スルホニル尿素薬(SU薬)
オイグルコン®︎錠、ダオニール®︎錠、アマリール®︎錠、アマリール®︎OD錠など
速効型インスリン分泌促進薬(グルニド薬)
グルファスト®︎錠、グルファスト®︎OD錠、シュアポスト®︎錠など
②−3チアゾリジン薬
アクトス®︎錠など
は体重増加を起こしやすいとされています。
ですのでよりしっかりとした食事管理と運動計画が大切になってきます。
一方で、
①−1DPP−4阻害薬
ジャヌビア®︎錠、グラクティブ®︎錠、ネシーナ®︎錠、ザファテック®︎錠、メリゼブ®︎錠など
②−1α−グルコシターザ阻害薬(α−GI)
グルコバイ®︎錠、ベイスン®︎錠など
②−4ビグアナイド薬
グリコラン®︎錠、メトグルコ®︎錠など
は体重が増加しにくく、
①−1経口GLP−1受容体作動薬
リベルサス®︎錠
②−2SGLT2阻害薬
スーグラ®︎錠、アプルウェイ®︎錠など
は体重低下を起こしやすいと言われています。
ですので、服薬している薬の種類によって栄養指導の仕方も変えていく必要がありますね。
運動時の低血糖と対処法
次に実際に運動する際に注意する症状についてです。
一番気をつけたいのは運動中の低血糖ですね。
運動中の低血糖は、食事前や就寝時、早朝空腹時、食事が遅れた時などに特に起きやすく注意が必要です。
またいつもよりたくさん運動をした日の夜間や翌朝にも起きやすいので注意しましょう。
特に夜間低血糖には注意が必要です。
症状としては、60〜70ml/dl未満でふらつきや脱力感、手足の震え、冷や汗などの交感神経症状が、
50ml/dlでは嗜眠(しみん)や集中力低下などの中枢神経症状が出始めます。
一緒に運動する方がいるときは、会話のやり取りで受け答えが悪くなったり、表情の変化に気をつけましょう。
もしも持続自己血糖測定器をつけている方は、容易に血糖が測定できるので、運動中時々血糖を確認してみましょう。
2型糖尿病で服薬のある方が運動する場合は、念のためブドウ糖10gやチョコレート、飴などを
常備携帯するようにしたいですね。
もしも低血糖を疑う症状が生じた際、経口摂取ができるようであれば
ブドウ糖10g摂取やブドウ糖を含む清涼飲料水150〜200mlを
摂取するようにしましょう。
ただし、清涼飲料水を摂取する際には注意が必要です。
清涼飲料水にはブドウ糖の含むもの(コーラなど)と、ショ糖を含むもの(コーヒーなど)があります。
ショ糖は二糖類という糖質に分類されますが、
②−1α−グルコシターザ阻害薬(α−GI)
(グルコバイ®︎錠、ベイスン®︎錠など)
を服用時には二糖類の分解吸収が阻害されているので、
ショ糖を含む清涼飲料水では低血糖改善効果が少なくなります。
その場合には必ずブドウ糖を摂取するようにしましょう。
ブドウ糖など摂取後15分程度安静にしても症状が続くときには、もう一度同じ処置を取りましょう。
それでも症状が改善しないときや、けいれんや意識障害があるとき、
ブドウ糖など経口摂取が困難な場合には、速やかに医療機関へ搬送するようにしましょう。
まとめ
糖尿病のある方は、医師による治療(投薬)と医師の観察のもと管理栄養士による食事療法、
健康運動指導士による運動実践が大切です。
無理のない計画を立てて、自分に合った運動を行なっていきましょう。
体験トレーニングで、あなたに合った正しいトレーニング方法をご提案します。
ご自身の体に合ったパーソナルトレーニングを知っていただくために、2種類の体験トレーニングをご用意しています。
フォーム以外でのお問い合わせ・申し込みは TEL:054-288-2278
対応時間:火〜金10:00〜21:00/土10:00〜17:00(日・月・祝祭日を除く)
静岡市駿河区のパーソナルジム『FLAT ONE』では、プロスポーツ選手も指導している専門知識・経験が豊富なパーソナルトレーナーがマンツーマンで指導いたします。20代〜80代の方まで、ダイエット、筋力アップ、健康増進、スポーツのパフォーマンスアップをサポートいたします。パーソナルトレーニングジム専用マシン・KINESIS ONE(キネシス ワン)を静岡で初めて導入するなど設備も充実。
ご利用いただいた皆様の声をこちらでご紹介しています。
あなたも静岡市駿河区で人気のパーソナルジムFLAT ONEで、パーソナルトレーニング体験から始めてみませんか?お申し込みはこちらから。