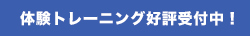現在地:HOME ≫ NEWS&TOPICS
【ブログ更新】筋トレしても筋肉つかない理由と効果的な対策法(後編)
筋トレしても筋肉つかない理由と効果的な対策法(後編)
前回のブログ「筋トレしても筋肉つかない理由と効果的な対策法(前編)」の続きです。

筋肉をつけるための実践的な解決方法
前編のブログで、筋肥大のメカニズムや筋肥大に必要な栄養について解説しました。
ですので、筋肉をつけるために何が重要か、ある程度お分かりいただけたかと思います。
大切なのは、筋肥大に適切な負荷(特に強度)で行うことと、適切な栄養摂取、適切なリカバリーの確保などです。
正しい筋トレ方法
前編の「筋肥大のメカニズム」で解説したように、筋肥大には、①最大張力 ②張力発揮時間の二つが重要です。
①は「挙上重量」や「トレーニング強度」に比例します。
筋力トレーニングで、「1回持ち上げる事が出来る最大重量」のことを、「最大挙上重量(1RM:1 Repetition Maximum)」と言います。
筋力を維持するために必要な強度(重量)は40%1RM以上とも言われますが、筋肥大のためには、その強度では不十分です。
トレーニング経験年数や体質などにもよりますが、最低70%1RM以上、トレーニング上級者であれば80%1RMが必要でしょう。
ただし、筋力トレーニングを始めたばかりの方は、関節の安定性に関与する、いわゆる「インナーマッスル」や軟部組織が弱い可能性があります。
いきなり高強度で行うと関節や、腱という筋肉と関節を連結している組織を傷めるリスクもあります。
トレーニングが初めての方は、50%1RM程度から始め、2週間おきに徐々に強度を上げていくようにしましょう。
身体が硬い方も同様です。
身体が硬い方は関節の可動域が狭く、高強度ではオーバーレンジ(過可動域)になってしまう可能性があります。まだトレーニング始めたばかりの方がオーバーレンジで高重量の負荷がかかると、怪我をするリスクが非常に高くなります。
身体が硬い方は、筋力トレーニングを行う際の可動範囲に注意して行いましょう。
そしてストレッチなどを並行して行い、柔軟性改善にも努めましょう。

次に②の張力発揮時間です。
バーベルを挙上する際に反動を使わずに行ったり、1セットあたりの回数(reps)やセット数を増やすほど張力発揮時間は長くなります。
筋肥大のためにどのくらいの回数やセット数が必要かは、様々な研究があり結論を出すのは難しい変数です。
トレーニングする方のトレーニング経験年数やトレーニング種目の配列、栄養摂取状態、睡眠の状態など様々な要素によっても変わってくると考えられます。
これまでの研究を総括してみると、1つの筋群あたり、1週間あたり10セット以上のトレーニング量が筋肥大を十分に起こすには必要なようです。
回数は、1セッションあたり40~60reps以上必要とする研究報告が多いようです。
ですが、やはり個人差がかなり大きいですので、こちらの数字を参考にして、ご自身でトレーニング量を変えてみて試してみるのが良いでしょう。
適切な栄養摂取
前回のブログで解説したとおり、筋肥大のためには「正のエネルギーバランス」が大切です。
いわゆる「ケトジェニック」の食事法でも"筋力"向上が図れるという報告もあります。ケトジェニックは基本的に脂質から多くエネルギーを摂取する食事法ですので、「正のエネルギーバランス」を保つことは可能です。
ですが、"筋肥大"できるかできないかという議論になれば、ケトジェニックに対しては否定的な報告が多いのが実情です。
十分な筋肥大を得るためには、やはり一般的なP:F:Cバランスを保ったうえで、「正のエネルギーバランス」を確保することが必要です。
どのくらいの「正のエネルギーバランス」が必要か、またタンパク質はどの位摂取すれば良いかは、前回のブログをご覧ください。

適切な休息とリカバリー
筋肥大に限らず、筋力向上のためにも、セッション間の休息期間や1セッションでのセットな間インターバルの時間は非常に重要です。
以前のブログ「筋トレは毎日続けた方が良いの?」で解説したとおり、筋肥大や筋力向上のためには、「超回復」をうまく利用するのが良いです。
トレーニングする筋群を曜日によって分けながら筋力トレーニングは毎日行うという実施方法や、1セッションあたりのセット数を3セット程度にして毎日行うなどといった実施方法もありますが、
基本的には1セッション実施したら2~3日間の間隔をあけて、1つの筋群あたり週に2~3回トレーニングするのが良いでしょう。
過多なトレーニングは逆効果です。
また、1セッションでのセット間インターバルの時間も重要です。
以前は、セット間インターバルの時間を短く(60秒以内)にした方が成長ホルモンの分泌が増したり、筋内の水素イオンの上昇(ph低下)や乳酸蓄積などの代謝ストレスによって筋肥大に効果的と言われていました。
ですが近年では、この考えはあまり支持されていません。
それよりも、セット簡インターバルを長めに(2分以上)取った方が、総負荷量(挙上重量と回数の乗数)が上がり、筋肥大にはより効果的とされています。
筋肉つかない原因

誤った筋トレ方法
前述した「正しい筋トレ方法」に適さない方法(強度やトレーニング量が不十分)では、筋肥大効果は小さいでしょう。
時々議論になりますが、「低強度・高回数(30%1RM程度で最大回数まで追い込む)」の筋力トレーニングは、筋肥大を目的にした場合は、あまりお勧めしません。
「低強度・高回数」の筋力トレーニングは、代謝ストレス(水素イオンや乳酸蓄積など)により、筋肥大が起こるとするエビデンスはありますが、主にⅠ型繊維(遅筋繊維)の肥大や筋グリコーゲンなど細胞内水分量の増加によるものだと考えられています。
筋肥大はⅠ型繊維よりもⅡ型繊維(速筋繊維)の方が大きく起こります。
筋繊維の元となる「筋衛星細胞」は、速筋繊維の方が遅筋繊維よりも筋力トレーニングにより大きく増加することが、多くの研究で示されています。
特別な理由がなければ、可能な限り、強度やトレーニング量を漸増させるようにトレーニングを進める方が良いでしょう。
適切な休息不足
筋力トレーニング経験がある方なら分かるかと思いますが、セット間インターバルの時間が短すぎると、高重量を数セット繰り返し上げる事は困難です。
例えば、100㎏を8回1セット挙げられたとしても、次のセットまでに60秒以内の短いインターバルでは、おそらく5回前後しか挙げれないでしょう。
短いインターバルでは一定のトレーニング強度を保つ事が出来ず、総負荷量が絶対的に下がります。
また、セッション間の休息期間(日数)が短すぎても、トレーニング強度を保てなかったり、オーバーワークに陥りやすくなります。
食事管理の問題
「タンパク質を摂っていれば、ダイエット中でも筋肉はつけられる」と思っている方を時々見受けますが、ダイエット中は「負のエネルギーバランス」になりますので、ダイエット中に筋肥大をさせることは基本的に難しいです。
タンパク質を適量摂っていても、負のエネルギーバランスでは筋肥大は期待できません。
ケトジェニックの場合も前述のとおり、"筋力アップ"はできるかもしれませんが、筋肥大はあまり期待できません。

体質や遺伝的要因
これまでに、「ACTN3(アクチニン3)」や「ミオスタチン」など、筋肥大に関与するであろうとされる遺伝子がいくつも発見されています。
「ACTN3」は速筋繊維に多く存在し、R型とX型があります。Rホモ型(RR)とヘテロ型(RX)の人は、高強度トレーニングによる筋横断面積の変化率が大きい傾向にあると報告されています。
また「ミオスタチン」は筋肥大を抑制するように働くとされており、ミオスタチンが少ない人の方が筋肥大しやすいと考えられています。
これら遺伝特性は、生来的なものですので、個人の努力で変えられるものではありません。
ACTN3は民間の遺伝子検査で簡単に検査可能です。
ただし、「私はACTN3がXX型だから筋肉はつかない」とか、「ミオスタチンが多いから筋トレしても無駄。」という事ではなくて、
ご自身の遺伝子特性に合わせてトレーニング方法や栄養摂取の仕方を選択するという考え方が良いかと思います。
必ずしも遺伝子検査をして遺伝タイプを調べる必要があるというわけではありません。
筋肥大に関わる遺伝子や体内のシグナル伝達系(タンパク質の合成や分解を促す酵素などの体内での代謝経路)は多数あります。
一つの遺伝子タイプだけで「筋肉がつきやすい」「つきにくい」と判断することはほとんど不可能です。もしも「筋肉がつきやすいか、つきにくいか」を遺伝子タイプで判断するなら、少なくとも5種類以上の遺伝子タイプを検査しないと判断はできません。
もしも民間の遺伝子検査をしたとしても、参考情報として留めてください。

また、速筋と遅筋の比率も、筋力トレーニングによる筋肥大にある程度関与すると考えられます。
平均的な速筋と遅筋の比率は、5:5〜6:4くらいです。オリンピックの陸上100mに出場するような「超瞬発力型」のような人は、7:3~8:2くらいとも言われます。
また速筋と遅筋の比率は、筋群によっても変わってきます。大胸筋、上腕三頭筋、大腿直筋、外側広筋などは速筋の比率がやや高く、上腕二頭筋、大腿二頭筋、ヒラメ筋などは遅筋の比率がやや高いと言われています。
前述したとおり、筋肥大は主に速筋で起こりますので、速筋の多い人の方が筋力トレーニングによる筋肥大は起こりやすいかも知れません。
ですが、遅筋の比率が多い人でも、速筋をしっかりと使うようにトレーニングすれば、筋肥大はできます。
速筋と遅筋とどちらが多いかを、簡易にテストする方法を「ベンチプレス」を例にしてご紹介します。
- 8RM(8回挙上できる最大重量)を測定する
- 次の計算式から、1RMを推定する
- (8RMの重量㎏)×0.033×8+(8RMの重量㎏)=1RMの推定重量㎏
このテストで算出した推定1RMの重量を行ってみてください。
3回以上挙上できる人は、速筋繊維の比率が高い可能性があります。
1回も挙上できなかった人は、遅筋繊維の比率が高い可能性があります。
もしも遅筋繊維の比率が高い可能性がある方は、以下をポイントに筋力トレーニングを行うことで、速筋繊維をしっかりと鍛えることができます。
- セット間インターバルを長めに取る(2分以上)
- ネガティブトレーニングを行う
① セット間インターバルが短いと速筋が回復せず、遅筋ばかりを優先的に使ってしまいます。結果として重量を下げざるを得なくなり、筋肉の発揮張力が小さくなります。総負荷量も少なくなります。
セット間インターバルを2分以上(5分以上のレストは筋音が下がるため避けましょう)取ることで、高強度で速筋を優先的に鍛えられます。
② 例えばベンチプレスの場合、バーベルを下げるフェーズをネガティブワークと言います。バーベルを下がるフェーズでは、筋肉が張力を出しつつ筋肉が伸ばされていきます。このような筋肉の収縮形態をエキセントリクス(またはエキセントリック収縮)と言います。
エキセントリクスでは速筋が優先的に使われます。
ですので、バーベルを下げるフェーズをややゆっくりと行ったり、自力で挙がらなくなってから補助者に補助してもらいながらネガティブワークを3回行うなどすることで、速筋繊維をしっかりと鍛えることができます。
また遅筋繊維は低強度・高回数で代謝ストレスを掛けるような筋力トレーニングで肥大しやすいため、高強度・低回数トレーニングと、低強度・高回数トレーニングを組み合わせることで速筋と遅筋を両方ともバランスよく肥大させることが出来るかも知れません。
有酸素性運動の影響
筋力トレーニングと持久力トレーニングを同時に行うことを「コンカレントトレーニング」と言います。
高強度の持久力トレーニングを伴うコンカレントトレーニングは、筋肥大の弊害になる可能性があります。
2012年に「コンカレントトレーニングが筋力向上を阻害するかどうかは、持久性トレーニングの時間と頻度に依存している」とする研究報告があります。
持久性トレーニングは、AMPKという酵素を活性化させます。
AMPKは、筋肥大に重要な役割を担う「mTOR」の反応を抑制します。
つまり、筋肥大が起こりにくくなります。
「週に2日以上、1日30分以上の持久性トレーニングを含めたコンカレントトレーニングは、筋力トレーニングのみを実施した場合よりも筋力向上や筋肥大が減弱された」という研究報告もあります。
低強度で短時間のジョギングやウォーキングなどは良いと思いますが、高強度の持久力トレーニングは、筋肥大の弊害になる可能性が高いです。
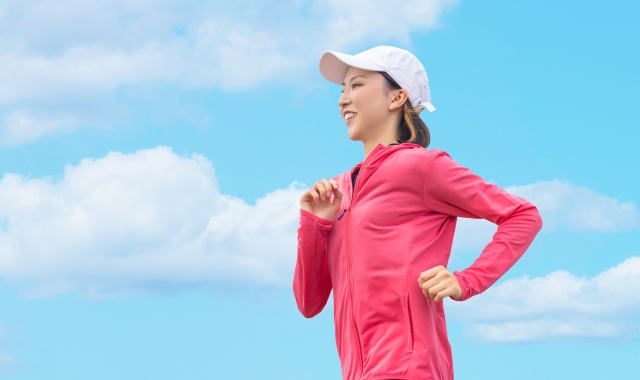
まとめ
筋肉がつかない理由と効果的な対策法について、理解していただけたでしょうか。
筋トレに取り組む際には、適切なトレーニングや栄養、休息などを心がけることが重要です。
無理な負荷をかけるだけでは効果が上がらず、リスクが高まることもあります。
適切な負荷と正しい方法でのトレーニングを意識して、長期的な視点で取り組みましょう。継続することで効果を実感できるはずです。
ご自身の筋肉がつかない原因を探り、トレーニング内容を修正することで、理想の筋肉を手に入れるための第一歩となるでしょう。
体験トレーニングで、あなたに合った正しいトレーニング方法をお伝えします
ご自身の体に合ったパーソナルトレーニングを知っていただくために、2種類の体験トレーニングをご用意しています。
フォーム以外でのお問い合わせ・申し込みは TEL:054-288-2278
対応時間:火〜金10:00〜21:00/土10:00〜17:00(日・月・祝祭日を除く)
静岡市駿河区のパーソナルジム『FLAT ONE』では、プロスポーツ選手も指導している専門知識・経験が豊富なパーソナルトレーナーがマンツーマンで指導いたします。20代〜80代の方まで、ダイエット、筋力アップ、健康増進、スポーツのパフォーマンスアップをサポートいたします。パーソナルトレーニングジム専用マシン・KINESIS ONE(キネシス ワン)を静岡で初めて導入するなど設備も充実。
ご利用いただいた皆様の声をこちらでご紹介しています。
あなたも静岡市駿河区で人気のパーソナルジムFLAT ONEで、パーソナルトレーニング体験から始めてみませんか?お申し込みはこちらから。