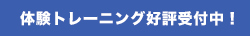現在地:HOME ≫ NEWS&TOPICS
【ブログ更新】膝の痛みの原因は、膝にあらず — 股関節・足首・体幹を整えて根本解決
膝が痛くても、原因が膝だとは限らない

多くの方が「膝が痛い=膝の軟骨・関節そのものに問題がある」と思いがちですが、実際には 膝以外の部位の動きや連動が原因となって、膝に過剰な負荷がかかって痛みが出ている ケースが少なくありません。
例えば、股関節や足首の可動域が制限されていたり、動きがスムーズでなかったりすると、膝が “代わりに” 動いたり支えたりして過剰な負担を背負ってしまいます。
股関節や足首の動きが悪いと、膝が代わりに頑張りすぎて痛みが出ることも多い。
- 股関節の動きが硬いと、歩行時や階段昇降時に膝まわりの負担が増える可能性があります。実際、「股関節周辺の筋力低下や異常な動きが膝の怪我・痛みに影響する」ことが示唆されています。 (※1)
- 足首を反らせる動き(足関節背屈)が硬かったり、機能が低下していると、膝にかかる地面からの衝撃をうまく吸収できず、膝の怪我のリスクが高まることが示唆されています。(※2)
- ある研究では、足と足首の痛みが、変形性膝関節症の発症と関連性があることが示唆されています。(※3)
つまり、膝が“被害者”のようになっていて、「膝以外の部位の筋力低下や機能低下」が“加害者”のようになっていることも多いです。膝痛を“膝だけで考える”と、根本改善を見逃してしまう場合があります。
動きのクセが痛みの原因のことも

膝の痛みが慢性的で「長く歩いていると痛くなる」「決まった動作で痛みが出る」なら、身体の“動きの連動”や“クセ”に原因がある可能性があります。
歩く・しゃがむ・立ち上がる。そのクセが膝に負担をかけていることも。
- 日常で「立ち上がるとき、膝が内側に入る」「しゃがむとき膝が前に出過ぎる」などのクセがありませんか?こういった動きのクセがあると、膝関節周辺に過剰なストレスを与えます。
- 足首が硬い(背屈制限がある)と、歩行時などに膝の過剰な捻じれ(膝関節の過剰な外反)が起きたり、膝に過度な負担がかかりやすく、膝の怪我につながりやすいことが示唆されています。(※2)
- しゃがむ・立ち上がるといった動作でも、股関節が硬かったり、臀部の筋肉が弱かったりすると、膝関節に"異常な動き”(膝関節の過剰な外反など)が起きやすく、結果、膝の痛みが出やすくなります。
- つまり、「膝が痛む=膝を守るために膝まわりの筋肉を鍛える」「サポーターをつける」だけでは不十分で、その前に「どう動いているか」「どこで無理しているか」を評価することが重要です。
鍛える場所を間違えない。

膝まわりの筋肉強化は確かに大切ですが、それだけでは「痛くなる⇒治療する⇒動く⇒また痛くなる」という悪循環を断ち切れないことがあります。
膝まわりの筋肉だけを鍛えても根本改善にはならない。
- 膝を支える筋肉(例えば 大腿四頭筋・ハムストリングス・内転筋群)ばかり意識して鍛えても、股関節・足首・体幹の制御が弱いままだと膝に“代償動作”が出続けてしまいます。
- 例えば、前述のように股関節周辺の筋力低下や、足首の背屈制限を放置したまま膝だけ鍛えても、膝の異常な動きや膝関節への過度な負担は軽減されないでしょう。
- また、体幹部のコントロール能力の弱さは、膝の損傷の予測因子になることが報告されています。(※1)
- だからこそ、膝まわりの筋力強化だけでなく“その上・その下”を含めた“動きの連動”を整えることが必要です。
まずは全身を整えよう。
膝の痛みを予防するためには、膝だけを見るのではなく、身体のつながりを考えて機能改善を図ることが鍵となります。
まず「膝以外」を見直すこと。身体はつながっている。
※(ご注意)以下のチャックは、専門的な内容が含まれ、一人で行うと膝へ負担をかけてしまう場合があります。理学療法士や柔道整復師、専門の知識を持ったトレーナーと行うようにしてください。
1.股関節の可動性・安定性をチェック
- 股関節がスムーズに屈曲・伸展・内外旋できているか。もしそれらの動きが硬ければ、それによって膝関節の異常な動きが生じやすく、痛みに繋がることがあります。
2.足首・足部の可動性・連動性をチェック
- 足首の可動性をチェックしましょう。特に背屈制限と痛みの有無は重要なチェックポイントです。
- 例えば、両足を揃えて立ち、踵を床につけたまま、臀部が踵に着くまで深くしゃがむことができなければ、足首の背屈制限がある可能性があります。(※すでに膝に痛みがある方は、深くしゃがむ動作で痛みが誘発される危険がありますので、無理に行わないでください。)
3.動きの“クセ”をチェック
- 立ち上がり・歩行・しゃがむ動作など、日常生活動作を一度チェックしてみましょう。
- 例えば、「しゃがむときに、両膝が内側へ曲がっていないか」
- 「片足立ちになった時に、骨盤が傾いたり捻じれたりしていないか」
- 「歩いている時に、上半身が傾いたり、左右に揺れていたりしないか」など。
- もしもそういった動きが見られれば、それが膝に負担をかける"動きのクセ”かもしれません。
4.体幹部のコントロール能力と安定感を鍛える
- 前述したように、体幹部のコントロール能力の弱さは、膝の損傷の予測因子になることが報告されています。(※1)
- 例えば、「フロントブリッジ」のような基本的な体幹トレーニングや、バランスボールに座ってバランス感覚を養うようなエクササイズも、膝痛の予防に良いかも知れません。
5.上記とセットで、膝まわりの筋肉をバランスよく鍛える
- 膝の機能改善のためには、上記の股関節・足首の可動性と安定性、動きのクセを見直しましょう。
- そして、「膝まわりの筋肉(大腿四頭筋・ハムストリングス・内転筋)」と「膝以外の筋力(股関節外転筋・臀筋群・ふくらはぎ・足底筋など)」をバランス良く鍛えましょう。
- ただし、膝の痛みが強い時に自己判断は禁物です。まずは医師の診断をしっかりと受けてから、理学療法士や専門俊樹を持ったトレーナーの指導の下、行うようにしましょう。
まとめ
- 膝の痛み=膝だけの問題、ではありません。股関節・足首・足部・体幹など “その上・その下” の問題があると、膝に過剰な負担がかかります。
- 日常動作(歩く・しゃがむ・立ち上がる)の“動きのクセ”が膝に負担をかけていることも忘れないようにしましょう。
- 膝まわりの筋肉だけを鍛えるのではなく、身体全体の動き・連動・安定性を整えることが、根本解決につながります。
- まずは「膝以外の部位の可動性」「動きのクセ」「体幹の安定」をチェック・改善してから、膝の筋力アップへ移りましょう。
参考文献
- Christopher M. Powers.The Influence of Abnormal Hip Mechanics on Knee Injury: A Biomechanical Perspective.Journal of Orthopaedic & Sports Physical Therapy.February 1, 2010Volume40Issue2Pages42-51.https://www.jospt.org/doi/10.2519/jospt.2010.3337(参照 2025-10-31)
- Jeffrey B Taylor.Ankle Dorsiflexion Affects Hip and Knee Biomechanics During Landing.Sports Health. 2021 Jun 6;14(3):328–335.
- Thomas Perry.New research reveals link between ankle pain and onset of knee osteoarthritis.NDORMS.16 November 2021.https://www.ndorms.ox.ac.uk/news/new-research-reveals-link-between-ankle-pain-and-onset-of-knee-osteoarthritis?utm_source=chatgpt.com,(参照 2025-10/31)
体験トレーニングをお試しください
ご自身の体に合ったトレーニングを知っていただくために、2種類の体験トレーニングをご用意しています。
体験トレーニングのお申し込みは、24時間受け付けております。
LINEからも承っております
※あなただけのスポーツジム『パーソナルジム FLAT ONE』は静岡県静岡市駿河区曲金にあります。葵区・清水区や静岡市外のお客様にもご利用いただいています。アクセスマップはこちら